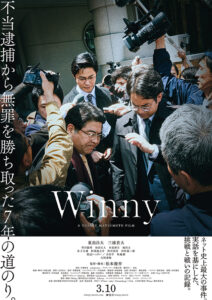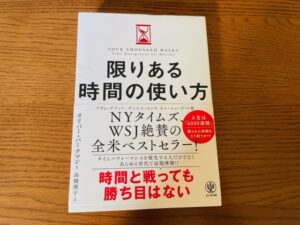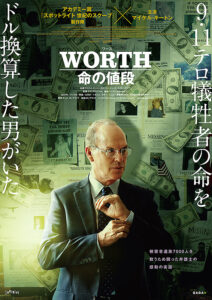当初、パート1は1924年から1959年まで書く予定だった。
書き進めるうちに予想以上のボリュームになったため、49年までに切り替えた。
意外と書くことがあった。
今回は1950年代の映画界を紹介したい。
50年代に入ると朝鮮戦争の影響もあるが景気も良くなってきた。
従って映画業界も活況になっていく。
この10年間は日本映画界にとってかなり恵まれ潤った時。
テレビもまだ普及していないので、娯楽の王様は映画。
1955年には1年間の映画館の入場者は延べ8億9400万人。
映画館も年々増加し5,182館に達したという。
終戦後から5倍になった。
ちなみに調べてみると、2022年の映画館数(シネコンが多いのでスクリーン数)は3,634。
映画館入場者数は1億5,252万人。
1955年の人口は約9,000万人。
この比較だけで、当時の映画の力がどれほど凄いのかが理解できる。
(書籍には書いていないっす)
1950年代半ばが映画界のピークだといっても過言ではない。
日本映画の製作も年間400本を超え、質・量ともに充実した時期。
僕が敬愛する黒澤明監督も「生きる」「七人の侍」「蜘蛛巣城」
「隠し砦の三悪人」と代表作を作っている。
日本映画史上最高傑作といわれる「七人の侍」は1954年のベストテンでは3位。
1位にはなっていない。
評価は後からついてくるのか。
その年の1位は木下恵介の「二十四の瞳」。
2位も木下監督だ。
そして、この50年代に圧倒的に評価が高かったのは今井正。
53年「にごりえ」、56年「真昼の暗黒」、57年「米」、
59年「キクとイサム」と1位を4回も獲得。
なんと57年は「純愛物語」が2位となりワンツーを独占。
この時代、世界的評価は黒澤明や小津安二郎の方が高い。
今井正は地味な存在。
僕も作品は観たことがないし、そもそも機会がない。
しかし、当時の日本映画ではダントツの映画監督といっていい。
外国映画に目を移すと全般的にアメリカ映画が不振。
年よって作品の出来は異なるが、59年はベストテンに1本しか選ばれていない。
1位の「十二人の怒れる男」のみであとはフランス映画やイタリア映画が中心。
2022年はベストテンのうち5本がアメリカ映画。
それが普通に感じるが、50年代は低迷していたようだ。
見方を変えればフランス映画やイタリア映画が今、不振なのか。
今でも耳にするフェデリコ・フェリーニやルネ・クレマンが躍動していた頃だし。
ようやく僕が昔観た映画が登場するのも50年代。
「第三の男」「風と共に去りぬ」「禁じられた遊び」「ライムライト」など。
52年の興行収入は「風と共に去りぬ」が1位だが、本作はベストテンには入っていない。
これも不思議な感覚。
不朽の名作に数えられる作品でも当時はさほど評価は高くなかった。
今も昔も同じなのは評価と興行収入は比例しないということ。
50年代ヒットした映画は大した評価は得ていない。
黒澤明くらいかな。
ヒットもし、上位にランクインするのは・・・。
ざっくりと1950年代をまとめてみた。
続く・・・。