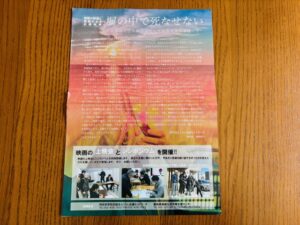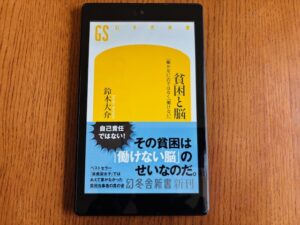3月下旬、あるシンポジウムに参加。
どこの会で紹介されたか思い出せないが、たまたま時間が合い縁遠い世界と思い参加したのだ。
それは「生きづらさを抱え窃盗を繰り返してしまう女性を支える」
と題されたNPO法人くらし応援ネットワーク主催のシンポジウム。
参加した理由の一つは映画の上映があったから。
「塀の中で死なせない」という実在した元犯罪者の生きる日々を追いかけた記録映画。
作品自体は自主映画に近く出演者はほぼNPO職員で構成。
ここで作品の出来栄えを問うのではない。
主人公の山本ミカさんの出所から施設で働き、ガンで亡くなるまでの2年6か月を忠実で描くことで、
支援者と当事者の苦難が明らかになる。
なぜ窃盗犯は再犯を繰り返すのか。
普通の生活を営む僕らには理解しがたいことが映画を通し理解できる。
同時期に読んだのが、「貧困と脳『働かない』のではなく『働けない』」。
真っ先に感じたのが2つの作品は共通点が多いということ。
タイトルだけ見れば別の世界を描いているようだが、根本は同じと映った。
僕らは自分勝手に犯罪者も貧困者も自業自得と思う面が多い。
僕もある程度、理解しているつもりでも自己責任いう考えは否定できない。
しかし映画や書籍を通して一方的な見方は誤りだと感じる。
犯罪者も貧困者も最初から望んでなる者は一人もいない。
本書では貧困に至るには「家族の無縁」「地域の無縁」「制度の無縁」と記しているが、
犯罪を繰り返す人もこれに近い。
そのような生活を背景に発達障害に陥るケースも多い。
そして、世間はそうした人に冷たい。
理解したつもりの僕でもそんな方が身近にいたら普通通り接することができるか。
表面上はできても自分の中に潜む従来の価値観を覆すことは難しい。
ただこの現実を受け止めることを止めてはいけない。
更生させようなんて強い正義感や貢献意欲は持ち合わせていないが、
自分に関わる人たちが前向きになれる行動はとりたい。
シンポジウムでは名古屋拘留所の幹部職員が「女性の窃盗犯税について」というテーマでも講演。
女性の犯罪で一番多いのは窃盗で60代以上の割合が最も高いという。
金銭的な理由ばかりではなく精神的な理由も多い。
むしろ20代の犯罪は減少傾向。
これも今の時代を表すことか。
小林さんは受刑者の生き方を2つの映画をネタに説明された。
「すばらしき世界」と「ヤクザと家族 The Family」。
この説明はとても分かりやすかった。
なるほどと納得。
とりとめのないブログになったが、最近、少し感じたことを綴ってみた。
本当は自称映画コラムニストとして書きたかったけど。
貴重な機会を頂き、ありがとうございました。