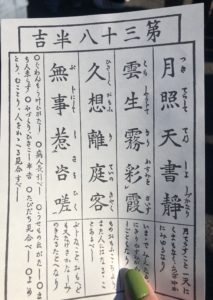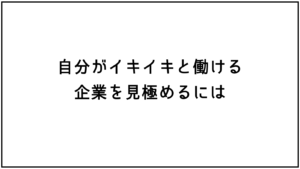誰にでも、どんなに親しくなっても、どんなに一緒に時を過ごしても、
その人との関係性において、何ほどかの「わかりあえない」何かが残る。
そんな感覚は、どんな人でも生きている行為の中で必然的なことだ。
そしてその「わかりあえない」という溝のようなモノを前にして、
なぜこの人はわかってくれないのか?
という違和感や問いを持って様々な対処をするだろう。
結果(データ)から、経験から、知識から、資質から、外部環境から、時代から、ときには運命から。
それらを処方箋に、社会的な「正しさ」のつもりで。
多くの人は自分で「正論」という答えのようなものを作り、
人に対して説得、交渉、対立、抑圧、忖度、迎合、無関心などの対応になる。
その答えで解決する場合、つまり具体的な問題やわかり合えないことに対して、
何かの答えがあって実行できて、かつ運が良い場合、それは上記のような方法で解決するだろう。
そしてそのノウハウのようなものが汎用化されて、一般化しそれをナレッジとして共有される。
多くの「わかりあえない」感覚は、上記の一連の行為によって霧散される。
それでいいのか?
本当にそれは「わかりあえなさ」に向き合っているのか?
そもそも他人との問題が、正論の取り合いの対立や紛争を巻き起こしていないか?
それはそもそも解決ではないのではないか?
これが従来の哲学的な「他者論」になるだろう。
そしてこの本の秀逸なところは、それを「現場」で働く他者との仕事の方法として語っているところだ。
哲学的な「他者論」を誤解を恐れず言うと「他者は理解できるはずがない」ということだ。
他者はあなたが理解できないから、他者なのだ。
それを容易な解釈や答えらしきモノをもとにしたアプローチは様々な誤解や対立や抑圧を生む。
著者は極めて高尚なことを問題にしているように見えるが、
この本はそれを極めて実践的に組織論という枠組みで仕事の実践知として考えようとしている。
ノウハウやスキルやデータで解決できることは、それで解決すれば良い。
しかし著者の言葉で言うなら「知識として正しいことと、実践との間には大きな隔たりがある」
そういう複雑で厄介な現場の問題は、「わかりあえなさ」から始まり、対話を通じて「適応課題」に取り組むことが重要だ。
問題なのは、一人ひとりがそれぞれの固有の「ナラティヴ」があることだ。
ナラティヴとはこれは難しい言葉だが、物語、つまりその語りを生み出す「解釈の枠組み」のことだ。
組織とは、いわば仕事をする人の関係性の総体のはずだ。
しかし組織には「私たち働く一人ひとりは組織を構成する部分であり、中心的な存在ではない」という組織にまつわる中心的なメタファーが存在している。
組織において「わかりあえなさ」は、現場の孤立、中間層の孤立、上司の孤立、部署間での軋轢、自己からの孤立(他責思考)など様々な適応課題というしかないような問題を引き起こしていると思う。
この本では自らのナラティブを一度横に置き、他者との対話を通じた言葉における関係性の再構築を通じて、自らのナラティブの偏りと向き合い、何かを生み出すことが大事だと促す。
対立を生む社会的な客観を根拠にするような批判(マウントの取り合い)よりも、
個人のナラティブを大事にした他者との対話による、会話を通じた「新たな現実を作ること」が最高の批判になるだろうと。
こういう他者に寄り添うような態度と組織論を融合する実践論として、大変参考になると思う。
以上、高井でした。